各種催事
- ホーム
- セミナー・シンポジウム
- パッケージデザイン懇話会
パッケージデザイン懇話会
2025年度 開催予定
| 例 会 | 第171回 講演会 |
第172回 講演会 |
第173回 講演会 |
第174回 講演会 |
|---|---|---|---|---|
|
日 程 ・ 時 間 |
5月19日 (月) 15:00~17:30 |
8月29日 (金) 15:00~17:30 |
11月25日 (火) 15:00~17:30 |
2026年 2月25日 (水) 15:00~17:30 |
今年度も昨年度に引き続き、基本として包装技術協会会議室での対面とオンラインでのハイブリッド開催を予定しております。
※交流懇親会の開催方法につきましては懇話会ニュースでお知らせいたします。
※日程及び時間は変更する場合があります。
2024年度 実績
|
第167回 講演会 会場開催とZoomによるハイブリッド講演 |
|---|
 テーマ:愛おしい、お菓子とパンの包み 講師:甲斐 みのり 氏/文筆家 参加者数:33名 講演概要: 幼い頃からお菓子の包み紙が大好きで、大切にとっておいて雑貨に作り替えて遊んでいた甲斐氏。おとなになってからはますます、お菓子の包み紙や缶の収集に没頭し、『お菓子の包み紙』(グラフィック社)など50冊以上の書籍を出版されている。“愛らしい“パッケージのお菓子や、レトロな地元パン®のデザイン、カプセルトイや文房具を実物を用いてご紹介いただいた。会場では静岡県富士宮市の最新の観光パンフレットを配布してくださり、地元の魅力の伝え方についてもご講演いただきました。 1)主な活動 ・書籍では京都の旅をテーマにしたものが多く、最近では建築関係や手土産に関するものを出版。 ・全国各地の観光案内冊子では、和歌山県田辺市や東京都の杉並区、宮崎県川南町などを手掛ける。 ・2020年には「歩いて、食べる東京の名建築さんぽ」を原案にした「名建築で朝食を」のドラマの監修を行った。全10話の中には手土産の情報についても忍ばせている。 ・カプセルトイの監修:「全国のかわいいおやつミニチュア」「地元パン ミニミニスクイーズ」「全国牛乳バッグ」など多数。 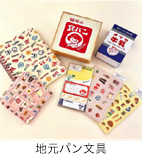
・地元パン®の活動:甲斐氏による「地元パン®」の定義は、昭和20年~30年頃までに創業したパン屋さんが作るパン。地域性や時代性や流行が込められており、地域の歴史や日本の流行を知る事ができ、パッケージの面白さがある。グラフィックデザインが仕事として確立していなかった時代なので、絵の得意な店主や地元の印刷会社の職人さんが描いたものが多く、大変素敵で魅力的である。そうしたパッケージを広く紹介する事で、食べる楽しみだけでなく、存在自体を愛でて地域を盛り上げる活動を続けている(地元パン文具の監修など)。 
・お菓子やパンのパッケージを活かした書籍の装丁:老舗の菓子屋の包装紙を表紙に使ったものを多数手がけた。 ・お菓子の包装紙を活かしたイベント:手紙社が開催する紙博で、お菓子の包み紙を再利用した封筒作りのワークショプを開催。ほかにも、京都・甘党市の古い学校の教室での紙袋コレクション展示や、ホテル雅叙園東京での地元パン袋コレクションの展示を行い、無名の職人によるデザインの、美術品と変わらない美しさを伝えてきた。 2)原点とものの捉え方 幼い頃から家庭では包装紙を大事に再利用する習慣があったため、美しく大切に取っておくものとして認識し、大学時代になってからお菓子のパッケージのコレクションを開始。住まいの大阪から東京までお菓子の包装紙巡りの旅を続ける中で、日本におけるパッケージとは何かを考えるようになった。その頃は、将来の仕事に思い悩んでいた時期でもあり、スケッチブックに自分の好きなモノや言葉で埋めていく「好きなもの探し」を行う。すると、近くの古い商店街で今まで何気なく見ていたものが色彩を帯びて、「加点法」でものを見るようになった。 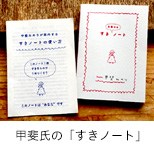
どのようなものでも、それを作った人の想いが宿っていると捉えられるようになり、先入観を持たずに土地柄や人柄をすくい取って見ている。 3)包装紙との関わり ・断捨離ブームではあるが、好きなものに囲まれて生きる幸せも大事だと感じている。しかし個人の収集には限界があるため「お菓子の包み紙」を出版し、旅の目的にして貰いたいと考えた。書籍化するために、包み紙データベースを作成し包装の種類や作家で分類している。 ・包装紙には商品と関わるストーリーやエピソードがあり、包装紙を見るだけで物語を感じられる。 ・ここ数年の昭和レトロブームで東郷青児氏のデザイン包装紙の人気が再燃し、20代の人が買いに来ている。 ・歴史のあるものだけでなく同世代の作家たちが手掛けた商品も好きだが、最近ではパッケージに力を入れるお菓子屋さんが増えており、コレクションが追い付かない状況。百貨店や駅や空港で新しいパッケージを探すのが至福の時間で新たな力を得ている。 ・また、ひとつの事が好きになると他にも興味が広がり、折り畳めるサンドイッチの箱も収集している。手提げ袋の形にも様々あり、考えられている人に敬意を感じている。  4)これまで書籍・雑誌・web等で取り上げてきた愛らしい包み紙 ・飴の専門店パパブブレの千葉限定「ザ・ピーナッツ・タフィー」、和歌山県田辺市の菓匠二宮「闘鶏まんじゅう」、別子飴本舗「別子飴」等を紹介。 ・富山「チージィーポッシュ」等、店舗を持たずに常に買えないお菓子の売り方が増えていたり、季節に応じてお菓子の缶の色を変える等、購買意欲が沸く工夫がされている。 ・千駄木のパン屋リバテイではキャラクターを用いたパン皿やパン雑貨を手掛ける。また推しているグッズを作りたいために、数量限定で自ら運営するサイトでWeb販売をしている。 
・メリーチョコレートが立ち上げた新ブランドの「ルルメリー」が今の推し。お菓子をきっかけにアパレルや雑貨店ではパッケージデザインを用いた商品が派生するほどブームを作っている。 ・コロナ禍以降の缶入りクッキーブーム(高級品)や、レトロ復刻されるお菓子、地域で廃業したパン屋さんの商品のパッケージの継承がされる例もある。 5)日々研究 ひとつ好きなものができると数珠つなぎになり、次に好きなものを育てることができる。好きの種を蒔いて人と共有し、お菓子のパッケージ好きなコミュニティを楽しみたい。その事を「ささやかな平和活動」と呼んでいる。好きなものを持っていると、人を批判したり争ったりせず平和に生きられるので、好きなものを増やす大切さを伝える活動をしている。 圧倒される程に強いパッケージ愛が伝わる講演でした。パッケージ会社で設計や開発に関わる身として大変光栄、且つ、改めてパッケージの力を認識できました。印象的な言葉は「誰かが付けた星の数を信じるよりも、自分の星を探して日々を過ごす方がずっと楽しい。」でした。人・もの・地域に真摯に向き合って来た事で軸ができ、ブレない信念が生まれるのだろうと感じました。星の数に惑わされること無く、ものを見る目を養って「ささやかな平和活動」を目指していきます。 (株式会社クラウン・パッケージ 加藤 友季子) |
|
第168回 2024年 8月30日(金)13:10~17:00 外部会場開催とZoomによるハイブリッド講演 講演会終了後、アサヒビール スーパードライミュージアム見学 |
|---|
 テーマ:飛ぶ動物と泳ぐ動物の機能的な流体力学デザイン 講師:田中 博人 氏 / 東京工業大学工学院機械系 准教授 参加者数:30名 講演概要: 今回の懇話会では、前半にアサヒビール研究開発センター(茨城県守谷市)の会議室にて講演(会場開催とZoomによるハイブリット講演)、後半は隣にあるアサヒビール茨城工場(スーパードライミュージアム)の見学を実施した。講演では、BSフジ「ガリレオX」にも出演し、生物が持つ機能や構造を取り入れた表面形状デザインを研究されている東京工業大学工学院機械系 准教授の田中氏をお招きし、これまで氏が研究対象としてきた様々な動物(蝶、イルカ、サメ、ペンギン)を題材に、「翼の動き」「体の流線形」「表面テクスチャ」をキーワードとして、流体力学デザインについて解説いただいた。 1.なめらかな流線形 ・流線とは、ある瞬間の流れを見た時、流れの速度ベクトルが接線である曲線と定義される。 ・流線形とは流線に沿った形であり、抵抗(抗力)が小さい。 ・風や水などの流体には粘性があるため、物体の周りに流体が流れている場合、流体の流れが剥がれ、後ろ向きの負圧が発生するため、物体には圧力抗力がかかる。また、物体表面と流体との摩擦による抗力もある。 ・流線形では、それによる圧力抗力は少なくなるので、表面の摩擦力の大きさが無視できなくなる。 ・なお、流線形は必ずしも薄くなくてよいため、厚くすることもでき、必要な強度を持たせることができる。 2.表面テクスチャについて ・サメの表皮の構造を研究。サメのうろこ(楯鱗)は種類によりいろいろな形状があるが、主にリブを利用したリブレットの構造により、乱流境界層における摩擦を低減しているのではないかと考えられた。 ・そこで、ホオジロザメの表皮のリブレット構造を解析したところ、それが大小2種類あり、それぞれサメの泳ぎの低速と高速に対応しているサイズであることがわかった。 ・まさに生物の形態は効率的な動きやエネルギーの消費を少なくすることに対応した、理にかなったものであることが、示唆された。 ・また、同様の検証をペンギンの羽毛の構造を模したリブレットでも実施。サメと同様に摩擦抵抗を若干ではあるが、減らす効果があった。ただ、ペンギンの場合はそれよりも、流れの変化に対応するロバスト性が高いことがわかった。 ・これは大海原を回遊し、長い距離を移動するサメと短い距離を俊敏に泳ぎ回るペンギンとの生態の違いを反映していると考えられた。 3.しなやかなはばたき翼 ・さらに、ペンギンの泳ぐ動きを研究。ペンギンは水中で羽ばたくことによって、翼に発生する揚力の前向きの成分によって前進している。その翼の形状をトレースし、ペンギン型ロボットを作って、同じような動き(泳ぎ)を実際の水中で再現することに成功した。 ・また、翼の動かし方を工夫することで、本物のペンギン以上の動きを実現できることも確認した。 ・なお、同じくはばたき翼を持つハチドリと比較すると、ハチドリの翼は空中で羽ばたくため、軽くする必要があり、薄い翼だが、ペンギンのそれは、より粘性の高い水中で羽ばたくため、強度を確保した分厚い翼になっている。 ・つまり、デザインが本質的に機能を有しているということであり、様々な生物の形態・デザインにはそれぞれ意味があると氏は仰っていた。 工場見学: 1時間半の講演の後は、スーパードライミュージアムに移動し、工場見学を実施した。工場見学の後は、試飲会場で出来たてのビールを味わいながら、会員同士の懇親を深めることができた。なお、試飲会場では、グラスに注いだビールの泡に、食べることのできるインクでデザインを印刷した、『泡アート』を体験した。 
最後に: 今回の懇話会では、弊社からの提案を幹事の方々とJPIの事務局の方々にご賛同いただき、外部開催とさせていただいた。初めての試みということもあり、どうなることかと不安もあったが、何とか大きな問題もなく、開催することができた。今回は、工場見学の都合上、会場参加の人数に制約があったが、会場参加いただいた方々には、今後の業務に活かすことのできるヒントや刺激を1つでも多く得ていただけたのであれば、企画した側としては幸甚です。 今後も参加される会員の皆様方にとって、有意義で魅力的な会となるよう、幹事の皆様やJPIの事務局と一緒に知恵を絞っていきたい。 (アサヒビール株式会社 宮下 裕介) |
|
第169回 2024年 11月26日(火) 15:00~17:30 会場開催とZoomによるハイブリッド講演 |
|---|

テーマ:ビジネス×デザインの「リアル」 山下 奉仁(ともひと)氏 / 日経デザイン編集長 参加者数:40名 講演概要:
消費者が価値を感じる対象がモノ(機能)からコト(体験)に移行し、広告イメージや企業理念に至るまで、一貫した体験の設計や、様々な部門の専門性を結集し、目に見えないものを形にするデザインの力が求められている。「日経デザイン」はデザイナーだけのためのメディアではなく、ビジネスのあらゆるシーンにおいて、デザインの視点を取り入れることで変革が起きている事例を豊富に紹介している。講演では、ここ最近の誌面制作で講師が実感した「ビジネス×デザインの『リアル』」を、8つのキーワードで紐解き、事例とともにお話しいただいた。 ■リアル① デザイナーはロジカルである 「マミーマート」のリブランディングを手がけた木原雅也氏は、膨大な情報を重要度別に整理しつつクリエイティブを作りあげ(23年3月日経クロストレンド特集「デザインファームに学ぶマーケ思考」)、佐藤オオキ氏と大改革に取り組んだカインズ土屋裕雅会長は、佐藤氏を「デザイナーというより、思考の壁打ち相手のようだった」と語る。(23年12月号特集「リブランディング×デザイン」) →顧客視点の提案が経営者にとっては重要なポイントになっている。 ■リアル② デザイナーは言葉の人である 水野学氏「企画書はラブレター」「自分の言いたいことばかり一方的に書いてある手紙なんて、誰も読みたがらない」。 木本梨絵氏は、ワークショップでの発言を発言者の名前と共に記載、キーワードは色分けして分類するなど、それぞれの発言との関係性がわかるように整理。(ともに、24年6月号特集「伝わるプレゼン」) →できるデザイナーは言葉で、ビジネス側とコミュニケーションをとっており、プロジェクト成功の要因ともいえる。 ■リアル③ 違和感、分かりにくさが心に刺さる アイフルのロゴマークに携わった北川一成氏は、「違和感のあるものが記憶に残る」という。(23年7月号特集「心理×デザイン」) ローソンZ世代向けチルド飲料「シトラスレモンティー」のパッケージは、動物が動物に気遣いするシーンを描いたイラストで、発信したくなるゆるさやシュールさがポイント。(23年7月号特集「売れるグラフィック」) →ロジカルの土台の上にすぐれた「?」(何だろう?と気になる)が生まれる? ■リアル④ プラスチックは悪なのか 吉泉聡氏は、人間が素材とどのように向き合うかを考え直すきっかけとなるよう、企画展「MATERIAL, OR」を考え、プラスチックマグを4950円で売るナガオカケンメイ氏は、「使い捨て」のプラスチック製品とは真逆の、小ロットの高価格商品(高ければ捨てられない)に挑戦。(ともに、23年11月号特集「素材と向き合う」) →プラスチックは悪なのではないかという考えに対して、消費者に価値とは何かを問いかけている。 ■リアル⑤ エクストリームユーザーにヒントあり シェーバーのグリップを握らず、ヘッド部分をつかんで使用する人が国内にも海外にも一定数いる、という調査結果に着目したことから、パナソニック「ラムダッシュパームイン」の開発につながり、新形状のシェーバーが登場した。(24年1月号特集「ヒット商品の裏にデザインあり」) →ロジカルに説明できるデータがあるからこそ、社内を説得できる。 ■リアル⑥ 個人からチームへ 自らを“クリエイティブアソシエーション”と表現するクリエイター集団「CEKAI」、様々なジャンルのプロデューサーが所属する企画集団「0100010(エンセンテン)」など、1人のクリエイターの感覚に依存せず、多様な専門家同士の共創によってプロジェクトを進めていくクリエイティブチームが増えている。(24年2月号特集「次世代を担うクリエイティブチーム」) →複雑化/多様化したプロジェクトは、専門性の高い個の力を結集したチームが必要になっている。 
■リアル⑦ 「観察」こそクリエイティブ 著書『観察の練習』で知られる菅俊一氏「どういった表現が人の行動や判断を促す手掛かりになっているか。それを発見する作業も『観察』」、「外界を観察することと頭の中でアイデアを考えることは、実は対象が違うだけで同じ行為ではないか」。(24年9月号特集「リサーチこそクリエイティブだ」) →思考は自分の頭の中の観察、気付くか気づかないか、概念的な理解だけではない。 ■リアル⑧ ブランディングは誰のもの? マーケターはブランディングができるのか? ブランドには色、形など顔となるものが必要で、そのイメージを作り上げるのはデザイナー。とはいえ、ブランド維持管理を含むブランディングはデザイナーだけでは困難で、双方からのアプローチで協力関係を築いていくのが最適ではないか。 ■まとめ デザインとビジネスの交点は? デザインサイドは元々「人間中心」であり、ビジネスマーケティングでもようやく当たり前になってきた。デザインとビジネスの交点は、さらに「人間を探究していく」ことではないだろうか。 【最後に】 講演では、ビジネス視点での「リアル」を具体的にお聞かせいただきました。講演後の質疑応答、会場参加者による懇親会においても活発な意見交換が行われ、充実した時間となりました。関係各位に御礼申し上げます。 (公益社団法人日本パッケージデザイン協会 中越 出) |
|
第170回 2025年 2月26日(金) 15:00~17:30 会場開催とZoomによるハイブリッド講演 |
|---|
 
テーマ:書体とパッケージ。デザインが果たす3つのミッション 講師:株式会社モリサワ 参加者数:43名 講演概要: 株式会社モリサワ(以下モリサワ)にてフォントの企画に携わられている阪本氏より、フォントの概要と開発の流れを解説いただきました。その後「プフシリーズ」をデザインされた富岡氏より、「守る」「伝える」「魅せる」をキーワードに実際のプフシリーズの開発秘話についてお話いただきました。 1. 阪本氏:モリサワフォントができるまで モリサワでは、ディレクター、タイプデザイナー、エンジニアがチームとなってフォントを開発。
「デザイン設計」:メインデザイナーが主要な文字を数百文字デザインする。  「検査」:誤字チェック、各種アプリケーションでの動作確認を実施。 読みやすい文字にするための各種調整(錯視調整、潰れ防止の処理等)が行われており、同じ「木」偏の文字でも同じ「木」の形はないそう。(右図参照) 2. 富岡氏:書体とパッケージ。デザインが果たす3つのミッション ~「プフシリーズ」の開発を通じて~ パッケージデザインと書体、いずれも「守る」「伝える」「魅せる」点で共通点あり。  「プフシリーズ」は2022年以降リリース。 「守る」:デザインとフォントファイルの品質を守る。 「伝える」:書体もメッセージを伝えている。 
「魅せる」:視覚的に魅力を引き出し、強く印象を与えるデザインのちから 
《講演を伺って》 普段何気なく見かけ、使っているフォントが、これだけのこだわりと多大な労力をかけて作られていることに大変驚きました。フォントの開発期間は2、3年かかる場合も多く、長いものだと10年近くかかっているとのこと。また、23,000字超もの文字をすべてチェックするその労力に頭が下がる思いです。自分の伝えたいメッセージを表現する手段として、今後フォントにもこだわってみたいと思います。 (株式会社一九堂印刷所 真山健) |
過去開催実績
| 開催回 | 開催概要 |
|---|---|
|
第155回 |
変更なし |
|
第156回 2021年 8月27日 |
パッケージデザインを巡る環境変化-afterコロナを見据えて 日経デザイン編集長 花澤 裕二 氏 |
|
第157回 2021年 10月27日 |
古くて新しいメカニズム、「形・構造・動き」の追求 法政大学 デザイン工学部 准教授 山田 泰之 氏 |
|
第158回 2022年 2月18日 |
食卓を彩る北欧のパッケージデザイン 加藤 真弘 氏 |
|
第159回 2022年 5月20日 |
農業のブランドデザインとパッケージデザイン (株)ファームステッド 阿部 岳 氏 |
|
第160回 2022 8月26日 |
Calbeeの「伝わるパッケージデザイン」の考え方 カルビー(株) 長澤 君枝 氏 |
|
第161回 2022年 11月25日 |
花王の「ESG経営」とインハウスデザイナーのモノづくり 花王(株) 平田 智久 氏 |
|
第162回 2023 2月17日 |
生活機能の変化を織り込み済みにするデザイン 東京工業大学 工学院機械系 西田 佳史 氏 |
|
第163回 2023 5月26日 |
AIやデザイン思考でパッケージデザインはどう変わるか (株)プラグ 代表取締役社長 |
|
第164回 2023 8月25日 |
サステナブルな容器包装への試行錯誤 (株)ロッテ 藤原 普夫 氏、飯田 智晴 氏 |
|
第165回 2023 11月28日 |
総合容器メーカーのデザイナーからの視点: 大和製罐の”内×外”の取組み 大和製罐(株)坂倉 由希子 氏 |
|
第166回 2024 2月28日 |
クライアントや印刷加工会社とのセッションから生まれるパッケージデザイン (株)BULLET 小玉 文 氏 |
入会ご希望の方は、ホームページの入会のご案内を印刷し必要事項をご記入の上パッケージデザイン懇話会事務局までメールまたはFAXにてご連絡くださいませ。
※パッケージデザイン懇話会事務局:井出 安彦
(E-メール ide@jpi.or.jp, Tel 03-3543-1189)