世界最大の日用消費財企業の一つUnileverは,最近,パッケージングの持続可能性目標を修正することを公表した。この動きは業界で大きな話題となっている。それは実際に何を意味するのだろうか?そして,これはパッケージのバリューチェーン全体に変化をもたらす可能性があるのだろうか?
まず,これまでのUnileverの持続可能なパッケージングのゴールがどのようなものであったのか整理してみる。同社は2018年に,2025年までに達成を目指す多くの目標を定めた。プラスチックに関しては,
1.自社の包装材を100%リサイクル可能,再利用可能,または堆肥化可能にすること
2.包装材に使用する化石由来のバージンプラスチックを2017年対比で50%削減すること(絶対量で10万トン以上)
3.自社のプラスチックパッケージに再生プラスチックを25%以上組み込むこと
などが含まれていた。
このうち,3番目の目標は恐らく達成できるだろう。Unileverはプラスチック再生材料の使用比率に関しては,2022年の21%から2023年には22%に若干ながら増やしており,この目標は射程圏にある。しかし,残念ながら残りの目標については先送りした。
Unileverは今回公表した新たな目標で,2番目の化石由来のバージンプラスチックの使用比率目標について,2026年までに30%削減,2028年までに40%削減すると下方修正した。また,1番目の100%再利用・リサイクル・堆肥化可能なパッケージの目標は,硬質容器については目標達成時期を2030年に,軟包装については2035年まで先送りした。特に異なる材料が複合化された軟包装材のリサイクルがいかに困難であるか,そして,まだどれだけの作業プロセスが残っているのか改めて認識することとなった。
これらの修正目標は,Unileverの新しい‘Climate Transition Action Plan’の重要な柱( https://www.unilever.com/sustainability/climate/our-climate-transition-action-plan/) となっており,先日の同社の株主総会で株主の98%の承認を得て可決された。しかし総会は平穏に進行されたわけではなく,Greenpeaceの活動家らが目標の修正に反対を表明した。
では,なぜUnileverはこれらの目標を修正することにしたのだろうか?
Greenpeaceなどの環境保護団体は,これは最近のUnileverの精彩を欠いた業績と株主からの圧力を反映したものであり,環境よりも収益を優先した典型的な例だと批判する。
しかし,このニュースを現実的な見直しだと評価する人達もいる。ニューヨーク大学のSternビジネス・スクールのAlison Taylor教授は,「企業が実際に影響力を行使できる問題について,冷静に現実的な決定を行うことは勇気ある行動として評価できます」と称賛する。「企業の社会的責任を広報活動の一環として扱う時代は終わりました。むしろ進歩としてとらえるべきでしょう」(Taylor教授)

Unileverもこの見解と同じ立場のようだ。Bloombergの最近のインタビューで,同社のCEOであるHein Schumacher氏は,現在の事業環境において従来の持続可能性目標を達成することはできないと答えている。「プラスチック包装に関しては同業者だけでなく,政府,小売業界と石油化学業界やプラスチック再生業界などバリューチェーン全体の連携が必須です。何よりも適切なリサイクル システムの整備を急がなくてはなりません」。
もちろんより広い視点で考えれば,そこにはUnileverのリーダーシップ構造の変化もあるだろう。2009年から10年間にわたり同社を率いた元CEOのPaul Polman氏と,2019年から昨年までCEOを務めたAlan Jope氏の下では,持続可能性と企業倫理が前面に押し出されたが,このアプローチには常に一部株主から不満があったのも事実だ。
さらにズームアウトすれば,包装の持続可能性目標を修正する消費財企業は,2025年を半年後に控え,これから増えていくだろう。
米国大手R&A企業GartnerのJohn Blake氏は一年以上前に次のように指摘している。「多くの企業が持続可能な包装の野心的な目標を,明確な根拠もなく設定しました。その結果,今になって彼らは掲げた指標を達成できない状況に直面しています」。
これは企業だけではない。スコットランド政府は,自らのネットゼロ目標を骨抜きにする政策変更を発表し,議会が混乱し最近数週間危機的状況に陥っている。
現在おかれている欧米の政治,経済,社会環境下では,理想主義よりも現実主義を優先せざるを得ない場面が増えている。しかし同時に,Unileverの前CEOのAlan Jope氏の「原則というのは,何かの犠牲を払う状況に直面して,初めて原則の重みを知ることができます」という言葉を改めて心に留めておくことは,価値があるだろう。
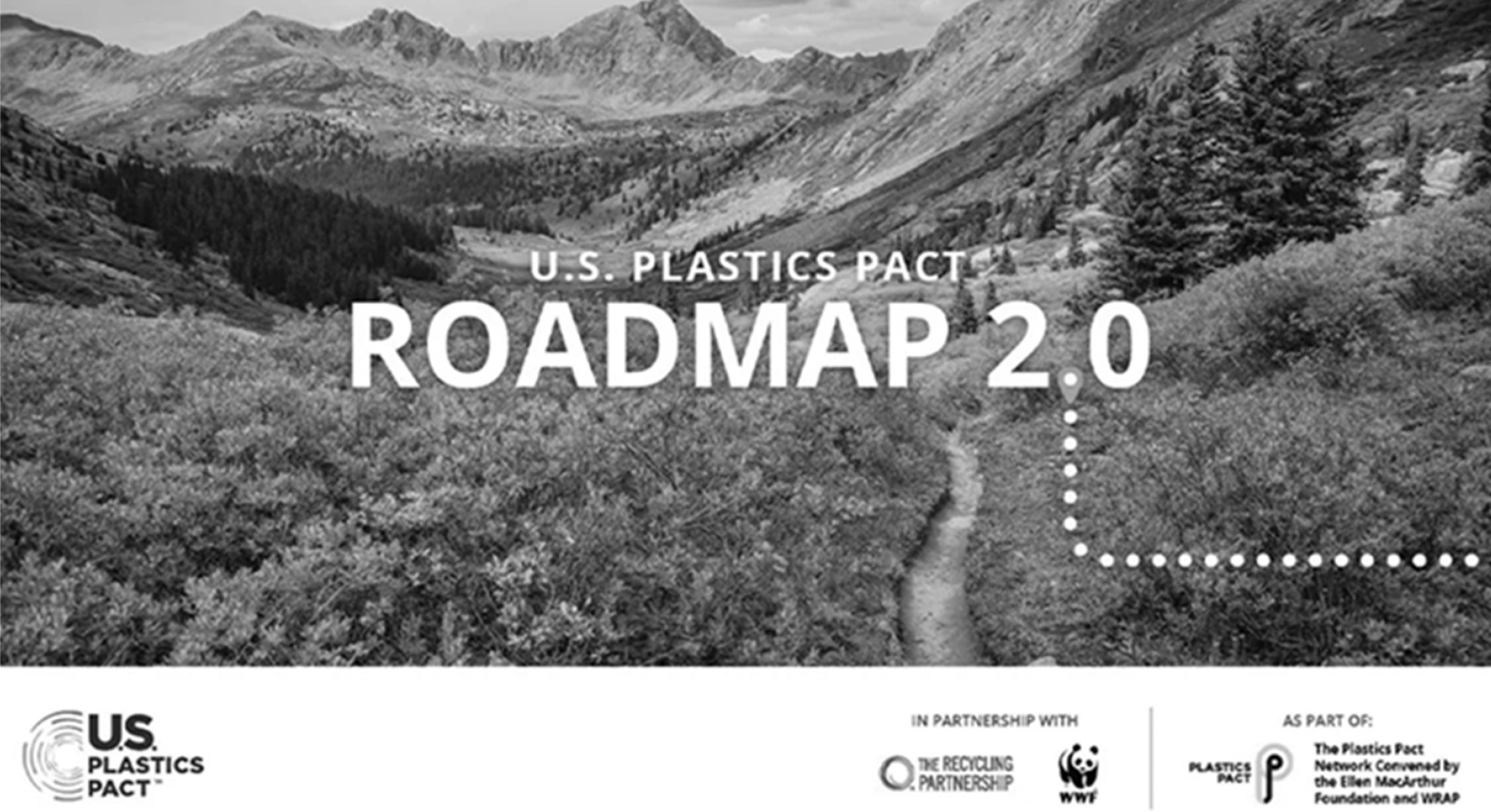
米国プラスチック協定(US Plastics Pact)も新しいロードマップを発表
米国の約1/3のプラスチック関連企業や業界団体が参加する米国プラスチック協定は,メンバー企業の総意として6月10日に,プラスチック包装の設計,使用,再生,再利用に関する戦略を更新した。新戦略では,達成未達が確実視されているこれまでの2025年目標のタイムラインを見直して,循環型包装の創出作業を継続する。
「ロードマップ2.0」と名付けられた新バージョンでは,2020年を基準年として,バージンプラスチック使用量の30%削減,プラスチック包装のリサイクル率50%の実現,さらに,プラスチック包装の原料に再生材料や責任ある方法で調達したバイオ材料を平均で30%使用することをゴールに,目標達成期限を2025年から2030年に再設定した。
「ロードマップ2.0」の新しい目標は,以前の「2025年までのロードマップ」の内容をおおよそ維持して,その達成期限を2025年から2030年に延期した。またいくつかの追加目標を加えている。
米国プラスチック協定は,エレン・マッカーサー財団の国際プラスチック協定ネットワークの一翼を担い,米国で「プラスチックの循環型経済」を目指すために結成された。メンバー企業の多くは,それぞれ独自の包装の持続可能性目標を掲げているが,パンデミックや長期化するインフレの影響を被り,さらには全米のリサイクルインフラが不十分な環境の下で苦しんでいる。目標達成のためにはバリューチェーン企業間や,同業種間のコラボレーションとイノベーションの強化と財源確保が欠かせない。
2021年に発表され,2020年を基準年とした当初のロードマップは,政府の規制に頼らず民間企業の自発的なプラスチックの資源循環に取り組みを標榜したものであった。2020年の設立当時のメンバー企業は62社であったが,現在では,その数は130社以上に達している。現在のメンバー企業,団体のリストには,包装コンバータートップのAmcor,食品トップのNestlé,小売り最大手のWalmartなどの有力企業や,米国飲料協会(ABA),米国コンポスト協議会(UCC)などの業界団体も名を連ねている。
米国プラスチック協定の理事長Emily Tipaldo氏(前職は米国化学工業協会の包装・消費財部門のトップ)は「ロードマップ2.0は2026年1月からスタートしますが,作業チームの活動は2024年6月から始めます。18ヵ月前倒しして,準備に十分な時間をかけ,メンバー企業間のコラボレーションの深化とイノベーションの推進により,目標を実現します」と述べ,2030年に向けて再スタートをきった。